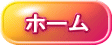第14章 御国の到来
はじめに
第14章は、「御国の到来(The Coming of the Kingdom)」であるが、ベルクーワの問題意識は、何か。すると、神の国、あるいは、キリストの国に関する事柄である。すなわち、主の祈りも、「み国を来たらたまえ」、「国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり」あるように、神の国、あるいは、キリストの国は、どのような性質(nature)のもかが問われる。また、神の国とキリストの国は、対立するのかどうか、また、神の国は、地上の国とどの程度類似性(analogy)をもつことができるかというようなことが、具体的に考察される。
1.神の国とキリストの国は、対立するのかどうか
(1)オスカー・クルマン
神の国とキリストの国は、対立するのかどうか。あるいは、換言すれば、キリストの国は、終末のときに神の国に吸収されるのかどうかという問題である。あるいは、さらに、神の子は、御父に吸収されるのかどうかの問題である。もっと簡単に言うと、パウロはコリント15:24-28において、「次いで、世の終わりが来ます。そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵を御自分の足の下に置くまで、国を支配されることになっているからです。最後の敵として、死が滅ぼされます。「神は、すべてをその足の下に服従させた」からです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身が、それに含まれていないことは、明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身も、すべてを御自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです」と言っているところの釈義、あるいは、解釈の問題である。
すなわち、ここは、終末には、キリストが御国を父に渡すことと、キリストが父に従属することが語られている。この意味を巡って、幾つかの神学説がある。そこで、ベルクーワは、整理して扱う。オスカー・クルマン(O.Cullmann)は、「新約聖書におけるキリストの王権と教会」(英訳 1956年)において、神の国とキリストの国、すなわち、神の支配とキリストの支配(regnum
Dei and regnum Christi)を明白に区別した。そして、両者は、内容から言えば、同じでないが、年代記的には(chronologically)、あるいは、時間の観点からは、区別されるべきもので、キリストの支配は今、しかし、終末には、キリストの支配は神の支配に入っていくと考えた。クルマンは言う。「時間の観点からは、キリストの国は、再臨までは、それ自身の力を表すが、再臨時には、終わりになる」。すなわち、今の時代は、キリストの支配、終末は神の支配が始まると考えた。
しかし、クルマンのこの考えには、批判が出た。たとえば、新約聖書は、神の国を将来のものとしてだけとは描いていない。パウロは、テモテ一1:17で、「永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように、アーメン。」と言って、神はすべての時代の支配者であることをはっきり言っている。また、キリストの今の支配には、父なる神の支配がないかどうかを考えなければならないなどと批判された。
しかし、では、クルマンの根拠は何か。それが、コリント一15:24-28である。キリストは御国を父に渡すというところである。そこで、クルマンは、これは、御子が終末には父に完全に吸収されてひとつになること(complete
eschatological absorption of the Son in the father)を表していると主張した。キリストの神性と父なる神が行動においてひとつになると考えた。
でも、ベルクーワは、パウロがここで御子は、御父に吸収されたり、消失(disappearance)したりすることを語っていない。キリストは、御国を父に渡すことが語られていると述べる。
(2)アンキラのマルケラス
アンキラのマルケラス(Marcellus of Ancyra)は、ニケア会議の三位一体論争に出てくる人物である。では、マルケラスはどのように考えたか。すると、キリストの中間支配(interim
theory)とも言うべきものを考えた。すなわち、ロゴスである神の第二人格(神の子のこと)は、救いの歴史においては、メシア・キリストとなって出現した。しかし、メシアとしては、救済のわざが終末に完了したときは、ロゴスは父なる神のところに帰って、父に吸収される。その結果、終末においては、父と子の区別はなくなるという理論を立てた。
ベルクーワは、このマルケラスは、キリストを被造物と考えたアリウスと同じ立場でなく、マルケラスは、逆に、キリストの神としての本質(homo-usios)を語ったアタンシウウスに賛成していた人であったので、誤解してはいけないと言う。いずれにしても、マルケラスは、御子が永遠にそのまま存在形態にあり続けるのではなく、御子に課せられた救済が終わった終末には再び父に戻って、父とひとつになることを主張した。
どうして、彼は、そのようなことを言ったのか。すると、コリント一15:28で、イエス・キリストは、御国を父なる神に帰すをそのように解釈したからである。
(3)ファン・ルーラー
ファン・ルーラー(A.A.Van Ruler)は、「律法の成就」(1947年)を書いた。また、「キリスト論における宇宙的なものと終末的なもの」(1962年)という論文を書いた。では、ファン・ルーラーは、どのように考えたか。すると、イエス・キリストの支配は今の時代で、終末になると、メシア・キリストは人間としての性質(human
nature)を失うと考えた。あるいは、人間性をもつ必要がなくなると考え、キリストの人間性の最後的辞任(eventual resignation
of his human nature)を主張した。ファン・ルーラーは言う。「彼は、メシアであることを止める。というのは、彼は、人々の存在の喜びによって、人々が神と小羊をあがめることができるようになるために、事柄をなされるようにすればよいからである」。すなわち、メシアとしての働きが終われば、人間性は、もう必要ないので、人間であることを止める。神であるだけでよいので、神だけに戻る。二性一人格でなくて、神性だけになる。
そして、これは、もちろん、イエス・キリストが世の終りに御国を父に渡すということを根拠にしている。そして、また、ファン・ルーラーは、カルヴァンも、御子は終末に人間性を脱ぎ捨てるという考えであったことを挙げている。ファン・ルーラーは、カルヴァンの「綱要 Ⅱ-14-3」から引用している。
カルヴァンは、コリント一15章の終末的視野に強い関心を持っていて、次のように述べた。キリストは、「仲保者の職務を果たしたので、彼の父の大使であることを止めるであろう。そして、彼が、世の創造以前に享受していた栄光で満足するであろう。・・・それから、また、神も、キリストの頭であること止めるであろう。というのは、キリスト御自身の神性は、今は、まだ覆いで覆われているが、それ自身で輝くであろう」。
また、カルヴァンは、コリント一15:27、28の註解で次のように述べている。「キリストは、今や、直接に、わたしたちと神との間にいるが、それは、彼がわたしたちを終りに父のところに連れて行くためである」。しかし、これは、いつの日か変わるであろう。「覆いが除かれるとき、わたしたちは神を、主権において支配しておられる神を、明白に見るであろう。そして、キリストの人間性は、より近く神を見ることからわたしたちを保つため、最早(no
longer)わたしたちの間にないであろう」。
カルヴァンのこれらの言葉から、ファン・ルーラーは言う。「キリストの肉的覆いは取り除かれる。というのは、キリストの人間性は最早媒介しないからである。仲保者のすべての役割は終わる」。すなわち、カルヴァンは、キリストは終末には、御国を父に渡して、御自分の仲保者職を終えて、人間性を脱いで、二性一人格を止めて、神性だけに戻ると主張した。
しかし、ベルクーワは、これはおかしいと言う。「しかし、カルヴァンは、キリストが人間性を捨てることについては何も言っていない。また、改革派神学の伝統においては、キリストの人間性の消失(perishability of Christ's human nature)の理念を支持するものは何もない」(432頁)。確かに、カルヴァンは、終末には、仲保者の役割が成就し、父への道が実際に開かれているときには、キリストの人間性は最早、神と人の間に立たないが、しかし、キリストが人間性を廃止する(abolition)というようなことは、カルヴァンは言っていないと述べる。
(4)コリント一15:24-28の解釈
では、コリント一15:24-28の正しい釈義、正しい解釈は何であるか。すると、ベルクーワは、その文脈は、キリストは、神に対するあらゆる敵を足台とするまでは、王として支配する。それから、終末がきて、キリストは御国を父に渡すのである。
そして、ここは、旧約聖書、詩編110:1から来ている。110:1は、「ダビデの詩。賛歌。わが主に賜った主の御言葉。『わたしの右の座に就くがよい。わたしはあなたの敵をあなたの足台としよう』」である。そして、「・・・あなたの足台としよう・・・」は、時間の制限を表しているわけではない。詩編の記者は、将来、すべての敵への完全勝利をするという視野で神の右へ祭司である王が着座することを描いている。すなわち、詩編110:1は、「・・・あなたの足台としよう・・・」とは言っても、時間のことを言っているのではなく、将来、すべての敵に勝利することを言っている。110:1の特色は、時間のことではない。
また、ヘブライ10:12も、「しかしキリストは、罪のために唯一のいけにえを献げて、永遠に神の右の座に着き」と詩編110:1を引用している。これは、別に、キリストの王としての支配権を制限しているわけではなく、将来の大勝利を視野に入れていることのである。その証拠に、キリストは、父の右に座すと言われている。すなわち、キリストは、御自分の栄光が全面的に明白に現わされることを待つと言われているのである。へブライ人への手紙の引用の特色は、キリストの王的支配を制限していない。
ところが、コリント一15章における詩編110:1の引用は、キリストが、父に御国を渡すということで、キリストの支配の終わり(end)を表している。では、これをどのように解釈するか。すると、教会は、コリント一15でも、キリストは、父に御国を渡すと言っているからといって、キリストの永遠の支配と対立するものと考えたかたと言うと、決してそんなことはしなかった。ルカ1:33に、「彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない」と言われているように、キリストの王権の永遠性を十分認めてきた。
(5)改革派神学者たちの解釈
改革派神学者たちも、キリストの支配をいろいろに区別してきた。たとえば、ヘルマン・バーフィンクは、「改革派教義学 Ⅲ」において、和解の媒介(mediation
of reconciliation)と結合の媒介(mediation of unity)に区別した。前者は、キリストの仲保による媒介の時代で今の時代を表し、後者は、キリストと父が結合して、媒介する時代で終末の時代を表すと考えた。
アブラハム・カイパーは、「口述教義学 Ⅴ」において、本質的支配(regnum essentiale)と経綸的支配(regnum oeconomicum)を区別した。前者は、創造に基づく支配で、終末に回復される支配を表し、後者は、救済の支配、すなわち、今の支配を表すと考えた。
しかし、バーフィンクやカイパーが、今の時代の支配と終末の時代の支配を区別するようなことをパウロはしていない。パウロは、明白に、コリント一15:28で、「・・・、御子自身も、すべてを御自分に服従させてくださった方に服従されます。・・・」と言っている。したがって、これは、明白な従属と依存を表している。そして、これは、強制や無理矢理でなく、キリスト自らの従順である。キリストは御父に従うのである。
キリストが御父に自ら従順に従うことは、パウロだけでなく、新約聖書に出ている。キリストは、しばしば、遣わされた者と言われているし、キリストの神性を否定することなしに、キリストが父に従っている姿は、福音書でも出ている。それゆえ、パウロがコリント一15章で言おうとしていることは、キリストのわざとキリストの御国の終末的完成を示そうとしているので、三位一体の問題や二性一人格のことを語ろうとしているのではない。すなわち、二性一人格のキリストの人格がどうなるとか、キリストと神との三位一体の関係がどうなるとかが語られているのでなくて、救いの経綸が語られている。
ベルクーワは言う。「こうして、ここでのパウロの思想方法にとって決定的なことは、救いの経綸の局面である。パウロは、終末、成就に考えを向けているのである。キリストとキリストの御国を過小評価しているどころか、逆に、キリストが父に御国を渡すそのときに、このことは事実としてキリストとその御国の栄光を強めているのである。キリスト中心主義対神中心主義、あるいは、キリストの支配と神の支配のジレンマは生じていない。すべては、救いを背負った現実となるところのものの実現に中心があるのである。このみわざは完成した、委任(mandate)は十分に達成されたということが―終末的に―今や、十分明白である。明らかに、三位一体内の神学の込み入ったことは、パウロの関心ではない。彼は、実現の現実と深さに関心をもっている。キリストが御国を父に渡すこと、また、キリストが御父に自ら従属することについてのパウロが語ることは、キリストの王権の現実性の基づいて描かれているところの新約聖書の他の終末論的視野と矛盾しない。終わりの全構造は、キリスト論的、そして、神論的に決定されている」(437頁-438頁)。すなわち、たとえば、黙示録21:23で、「この都には、それを照らす太陽も月も、必要でない。神の栄光が都を照らしており、小羊が都の明かりだからである」と言われていて、神と小羊が共に並んで述べられていて、対立、矛盾はない。
ベルクーワは言う。「終末の全構造は、キリスト中心的に決定されており、また、神中心的に決定されている。そして、黙示的言語が、ひとつの栄光(one
glory)であるものを描写するイメージの多様性に帰する。何故なら、キリスト中心的なものは、神中心的なものと対立して立たないからである(参照 黙示録22:5で、「神である主(the
Lord God)が僕たちを照らし」、黙示録21:22で、「全能者である神、主と小羊(the Lord and the Lamb)とが都の神殿だからである」(438頁)。すなわち、黙示録21:22では、「・・・小羊が都の明かりだからである」と言われているが、黙示録22:5では、「・・・神である主が僕たちを照らし・・・」と言って、小羊と神を入れ替えて語っていて、神とキリストの間に対立、矛盾、相互排他性がまったくない。すなわち、ひとつの栄光がキリストの栄光として、また、神の栄光として語られているのであり、両者に対立、矛盾、相互排除はまったきないのである。
ベルクーワは言う。コリント一15章において、「・・・パウロのポイントは、キリストの完成されたみわざとキリストの勝利の全体性の栄光に基づいて、神の視野がすべてのすべてにおいて明らかにされることなのである。そして、これこそ、終末についてのパウロのどんなに例外的な表現が、他の新約聖書が語るところのものと比較されるかもしれないが、それは、全新約聖書が小羊の神中心的象(the theocentric figure)の全終末において支配している仕方で描写している、イエス・キリストのみわざの実現成就を捕えることを示しているのである」(439頁)。
こうして、ベルクーワは、キリストの国と神の国の対立はなく、コリント一15章において、パウロは、キリストのみわざとキリストの御国の完成を語っていると解釈すべきであると述べる。コリント一15章は、時間を語るのでなく、キリストの御国の完成と勝利を語るのである。
2.神の国は、この世の国とどのような類似性をもつのか
(1)イスラエル王国の成立
神の国は、この世の国とどのような類似性をもつのか。あるいは、神の支配は、この世の王の支配とどのような類似性をもつのか。この問題を考えるにあたっては、イスラエルの歴史における地上の王国の機能がメシアの王国をどのくらい映し出すかを考えることになる。ベルクーワは、幾つかのことを挙げる。まず第1に、神の国は、神御自身が出たものであるが、イスラエルにおける王国はどうして出たか。すると、イスラエルは、神が王となって治めることをイスラエルの人々が十分に理解しなかったことから出た。士師記8:22、23で、「イスラエルの人はギデオンに言った。『ミディアン人の手から我々を救ってくれたのはあなたですから、あなたはもとより、御子息、そのまた御子息が、我々を治めてください』ギデオンは彼らに答えた。『わたしはあなたたちを治めない。息子もあなたたちを治めない。主があなたたちを治められる』」とある。人々は、神がイスラエルを治めていることを十分理解しなかったので、ギデオンが王となって治めることを求めた。
後に、サムエル上8:6-8で、「裁きを行う王を与えよとの彼らの言い分は、サムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。「民があなたに言うままに、彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上にわたしが王として君臨することを退けているのだ。彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、彼らのすることといえば、わたしを捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。」とある。ここでは、イスラエルが王を求めることは、神を捨てることと同じであることが記されている。目に見えない神への不信仰が目に見える王を求める動機になっている。
そして、さらに、後になると、イスラエルの人々の求めに応えて、サウルが預言者サムエルに油注がれて王になる。しかし、王を求めることが、神に対する不信仰であることを自覚して、イスラエルの人々は、自ら語った(サムエル上12:19)。
以上のようにして、イスラエルにおいても、王の制度は、そして、王国が出現するが、ベルクーワは、イスラエルが失敗したのは、王を求める動機(motivation)は、不信仰から求めたので悪かった。民の上に代表的かつ中心的統治を設けること自体が悪かったのではない。その証拠に、驚くべきことに、王国の願いはヤハェ御自身によって実現されていった。
(2)イスラエル王国は、メシアの国と類似性をもつか
そこで、では、イスラエルに生じた地上の王国は、メシアの国と類似性をもつか。あるいは、逆に、対照的性格をもつか。ベルクーワは、どちらもあると言う。メシアの国は、イスラエルという地上の王国と類似と対照の両方で考えられる。すなわち、相対的ではあるが、王が神に依存している限りは、メシアが神に依存しているから、類似性がある。しかし、サウロのように神に背くようになっては、最早メシアの国の類似性はない。そして、次第に、イスラエルは神から離れていく。離れれば離れるほどメシアの国との類似性はなくなる。そこで、ホセアも、8:4で、「
彼らは王を立てた。しかし、それはわたしから出たことではない。彼らは高官たちを立てた。しかし、わたしは関知しない。彼らは金銀で偶像を造ったが/それらは打ち壊される。」と言っている。
したがって、イスラエル王国は、神の支配と常に類似していたわけではない。確かに、イスラエルが神に依存している限りは類似していた。しかし、イスラエル王国は、神に背き、最後には、離れてしまったので類似していない。むしろ、永遠にまで神の国と対照的であるということになる。
(3)新約聖書は新しい王を描く
新約聖書は、旧約聖書の地上の王とは違った新しい王としてのイエス・キリストの出現を語っている。イエス・キリストトいうメシア的王の素晴らしいところは、無限の支配権をもっているところである。具体的には、王でありながら、預言者職、祭司職をもっていた。したがって、地上の王は、最早メシア王との類似をもたない。むしろ、キリストの偉大性を対照的に表すこととなる。
(4)イエスの出現によりメシアの国が始まる
イエスの出現とともにメシアの国が始まる。このメシアの国は、力だけでなく、栄光をはじめとするいろいろな徳、たとえば、義、喜び、平和などとともに考えるべきであって、メシアは王だから、あるいは、メシアの国は、力ある国という風に、力だけを孤立化させてはいけない。
何故このようなことを言うのか。すると、王と国と言うと、人はすぐに王の力(power)、あるいは、国の力を考える。政治学において、王、支配者、国家と言えば、人はすぐ力、パワーを第一に考える。
そして、もちろん、メシアと王であり、また、メシアの国も国だから、支配と力、パワーがある。しかし、パワーだけ取り出して地上の奇形的国家の暴君のような力を考えてはならない。地上の国家は、それでも、成り立つが、メシアの国、神の国は、暴君的パワーでは成り立たないので区別すべきである。
新約聖書において、神のことを「王の王」(テモテ一6:15、黙示録17:14)、「代々の王」(黙示録15:3)と言っている。これは、地上の王のように、暴君的なことを言っているのではない。しかし、メシアの国、神の国には、信仰による感謝とか頌栄とかがあるので違う。
ベルクーワは、神の力を孤立させて、神は何でもできるというスローガンを立ててやることは、正しくない。神の力は、神が人を助けること、神が人々を救うこと、神が人々を困難から救い出してくださることに表れるので、ただ、神は何でもできるというのは抽象化になる。
(5)神の国は、いろいろな言い方で語られる
神の国と結びつけて、聖書では、いろいろな言い方でなされている。神の国を受け継ぐ、神の国に入る、神の国の福音、パラダイス、神の国は言葉でなく力である、神の国は義と平和と聖なる喜び、堅固な土台を持つ都(ヘブライ11:10)、天の故郷(ヘブライ11:16)、新しいエルサレム(黙示録3:12)。いずれにしても、神の国の栄光や美しさがいろいろな言い方で、多様に言われているので、力だけで、神の国を考えない。神の国の豊さがいろいろある。神の国は、力とともに栄光で考えることが大切である。
(6)神の国は神中心
神の国というのは、もちろん、神中心である。神の栄光に満たされているが、しかし、神の国は、そこでは、信仰者も、また、そこで栄光を受けると言われている。それゆえに、神の国は、神の栄光は人の栄光と対立するというようなことはない。神の栄光は、人の栄光を含む。
3.神の国の到来を祈る
教会と信仰者は、主の祈りにもあるように、「み国を来たらせたまえ」と真剣に祈って、キリストにおいて始まった御国が完成するように、信仰によって求めていくべきである。そして、今、毎日を生きるための慰めと励ましとして歩むべきである。キリストによって開始されたものの完成である終末を信仰によって望み見て、今を生きていくのが、信仰ということになる。終末待望をもたない信仰にしてはならない。
結び
以上が、第14章「御国の到来」であるが、要旨を振り返ってみよう。ベルクーワの問題意識は、神の国、あるいは、キリストの国は、どのような性質のものか、また、神の国とキリストの国は、対立するのかどうか、また、神の国は、地上の国とどの程度類似性をもつことができるかを具体的に考察することである。
簡単に言うと、パウロが、コリント15:24-28で語っていることの解釈、釈義の問題である。特に、「・・・そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。・・・すべてが御子に服従するとき、御子自身も、すべてを御自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです」と言っているところの釈義、あるいは、解釈の問題である。
クルマンは、これは、御子が終末には父に完全に吸収されてひとつになることを表していると主張した。キリストの神性と父なる神が行動においてひとつになると考えた。でも、ベルクーワは、パウロがここで御子は、御父に吸収されたり、消失いたりすることを語っていないと批判する。
ニケア会議の三位一体論争に出てくる人物で、アタナシウスに賛成していたアンキラのマルケラスは、キリストの中間支配とも言うべきものを考えた。すなわち、ロゴスである神の第二人格(神の子のこと)は、御子が永遠にそのまま存在形態にあり続けるのではなく、御子に課せられた救済が終わった終末には再び父に戻って、父とひとつになることを主張した。
ファン・ルーラーは、メシアとしての働きが終われば、キリストの人間性は、もう必要ないので、人間であることを止める。神であるだけでよいので、神だけに戻る。二性一人格でなくて、神性だけになると、カルヴァンに訴えて主張した。しかし、カルヴァンは、そのようなことを語っていない。
バーフィンクは、和解の媒介と結合の媒介に区別した。前者は、キリストの仲保による媒介の時代で今の時代を表し、後者は、キリストと父が結合して、媒介する時代で終末の時代を表すと考えた。カイパーは、本質的支配と経験的支配を区別した。前者は、創造に基づく支配で、終末に回復される支配を表し、後者は、救済の支配、すなわち、今の支配を表すと考えた。しかし、バーフィンクやカイパーが、今の時代の支配と終末の時代の支配を区別するようなことをパウロはしていない。
では、コリント一15章の正しい解釈は何か。すると、ベルクーワは、キリストの国と神の国の対立はなく、パウロは、キリストのメシアとしてのみわざとキリストの御国の完成を語っていると解釈すべきであると述べる。コリント一15章は、時間を語るのでなく、キリストの御国の完成と勝利を語るのである。キリストの完成されたみわざとキリストの勝利の全体性の栄光に基づいて、神の国と神の栄光がすべてのすべてにおいて明らかにされるのである。すなわち、ひとつの栄光がキリストの栄光として、また、神の栄光として語られているのであり、両者に対立、矛盾、相互排除はまったきないのである。
ところで、神の国は、この世の国とどのような類似性をもつのか。あるいは、神の支配は、この世の王の支配とどのような類似性をもつのか。すると、イスラエルにおいても、王の制度と王国が出現するが、ベルクーワは、イスラエルが失敗したのは、王を求める動機は、不信仰から求めたので悪かったが、民の上に代表的かつ中心的統治を設けること自体が悪かったのではない。その証拠に、驚くべきことに、王国の願いはヤハェ御自身によって実現されていったことを述べる。
イスラエル王国は、神の支配と常に類似していたわけではないが、イスラエルが神に依存している限りは類似していた。でも、イスラエル王国は、神に背き、最後には、離れてしまったので類似していない。むしろ、永遠にまで神の国と対照的であるということになる。
そして、新約聖書は、旧約聖書の地上の王とは違った新しい王としてのイエス・キリストの出現を語っている。イエス・キリストトいうメシア的王の素晴らしいところは、無限の支配権をもっているところである。具体的には、王でありながら、預言者職、祭司職をもっていた。したがって、地上の王は、最早メシア王との類似をもたない。むしろ、キリストの偉大性を対照的に表すこととなる。
こうして、イエスの出現とともにメシアの国が始まるが、メシアの国は、力だけでなく、栄光をはじめとするいろいろな徳、たとえば、義、喜び、平和などとともに考えるべきであって、メシアは王だから、あるいは、メシアの国は、力ある国という風に、力だけを孤立化させてはいけない。聖書では、神の国と結びつけて、いろいろな言い方でなされている。神の国を受け継ぐ、神の国に入る、神の国の福音、パラダイス、神の国は言葉でなく力である、神の国は義と平和と聖なる喜び、堅固な土台を持つ都、天の故郷、新しいエルサレムなどであり、神の国の多様な豊さを教えている。
また、神の国というのは、神中心であり、神の栄光に満たされているが、しかし、信者も、また、そこで栄光を受けるので、神の栄光は信者の栄光と対立せず、信者の栄光を含む。
教会と信仰者は、「み国を来たらせたまえ」と日々真剣に祈って、キリストにおいて始まった御国が完成するように、信仰によって求めて、毎日を生きるための慰めと励ましとすべきである。終末待望をもたない信仰にしてはならない。
以上が、第14章「御国の到来」の要旨である。終末論を締めくくるにふさわしい主題と内容であると思う。ベルクーワの「教義学研究シルーズ」の第1巻として出版された「信仰と聖化」(英訳)のカバーを見ると、ベルクーワの「教義学研究シリーズ」の今後の出版される著作予定が載っているが、その1冊として「神の国」(The Kingdom of God)が挙げられているのを見る。したがって、最初、ベルクーワは、神の国について1冊を書くつもりであったと思われる。しかし、実際には、1冊の著作としては現れなかった。でも、神の国についてのある部分のことは、この「キリストの再臨」の第14章「御国の到来」で書いたのではないかと思う。
そして、この第14章「御国の到来」においては、神の国とキリストの国との関係、あるいは、神の支配とキリストの支配の関係はどのようなものかが扱われているが、この問題は、ベルクーワの「教義学研究シリーズ」の「神の摂理」の第4章「統治としての神の支配」においても、扱われている。
「神の摂理」の第4章「統治としての神の支配」においては、イエス・キリストの支配と神の支配との関係は、国家のキリスト論的基礎づけの問題と関連として、特に、20世紀の弁証法神学のカール・バルトなどによって提出された問題であったが、ベルクーワは、これらの問題を摂理論の中で、神の統治としての関連において扱い、キリストの支配と神の支配との関係は、ハイデベルク信仰問答の50問を手がかりにして、考えて、神はキリストにおいて、また、キリストによって支配する(God
rules in and through Christ)ことを語った。
確かに、キリスト出現までも、キリスト出現後も、神は主権者として変わらずに支配している。しかし、仲保者のイエス・キリストが出現し、イエス・キリストが十字架の死と復活を経て、昇天して、父なる神の右に座したことによって、神の支配の仕方・様式に変化が生じた。すなわち、それまでは、仲保者的でなかった支配であるが、イエス・キリストの昇天後、神の支配は、イエス・キリストを通す仲保者的支配になったのである。仲保者的でないものが、仲保者的になったのであると述べた。
ベルクーワの「教義学研究シリーズ」の「神の摂理」の第4章「統治としての神の支配」における神の国とキリストの国との関係、あるいは、神の支配とキリストの支配の関係はどのようなものかについての詳しい議論は、当該個所をぜひお読みください。
他方、この「キリストの再臨」の第14章「御国の到来」においては、コリリント15章の「・・・キリストは、・・・父である神に国を引き渡されます。・・・御子自身も、すべてを御自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです」に基づき、あくまで、終末におけるキリストの支配と神の支配の関係が扱われている点で、「神の摂理」の第4章「統治としての神の支配」におけるキリストの支配と神の支配との関係とは違った観点からの問題となる。
そして、ベルクーワは、終末においては、キリストがすべての敵を滅ぼして、国を父に渡し、御自身が御父に自ら服従することによって、キリストの救いのみわざがすべて勝利し、完成することによって、キリストの栄光が表れ、同時に、御父の栄光がすべてにおいて明らかになることを語っていると述べる。
すなわち、ある人々が主張したように、キリストが、メシアの職務を終わったので、もはやメシアである必要がなく、それゆえに、キリストは人性を脱いで、神性に戻るかとか、さらに、父なる神に吸収されて父とひとつになるとかの三位一体内関係の込み入った事柄を教えているのでなくて、キリストが、すべての敵を滅ぼして勝利して、救いのみわざを完成させたことによって、キリストの栄光が表れ、さらに、御子御自身も神に自ら服従することによって、神の栄光がすべてにおいて表れることを教えているのであると主張する。
すなわち、ひとつの栄光が、また、ひとつの御国が、また、ひとつの支配がキリストによっても、神によっても表わされるのである。こうして、終末はキリスト中心的であるとともに神中心的でると述べている。両者に、対立、矛盾、相互排除はないのである。ひとつの栄光、ひとつの御国、ひとつの支配がキリストから、また、同時に、神から見られているのである。
わたしたち日本キリスト改革派の牧師にとっては、キリストの支配権という言い方よりもキリストの王権という言い方の方が、ピンと来るかもしれない。わたしたちの改革派神学においては、伝統的に、仲保者イエス・キリストが、メシアとしての職務を果たすために三つの職務、三職をもっていると考えてきたが、それらは、預言者職、祭司職、王職(the kingly office)である。そして、キリストの支配権は、キリストの王職に属する王権(the kingship of Christ)と言ってきた。
では、わたしたち、日本キリスト改革派の信仰規準であるウェストミンスター信仰基準において、コリント一15:24-28は、どのように解釈されているか。すると、4個所で出てくる。まず、ウェストミンスター信仰告白第8章「仲保者キリストについて」の第8節の「・・・彼らのすべての敵を征服することによってである」の証拠聖句として、コリント一15:25、25が挙げられていて、キリストは、選民の敵を征服して、選民のあがないを守ってくださることが表明されている。この第8節は、キリストの王権を直接語る意図でなく、ウェストミンスター信仰基準作成当時の仮説的万人救済論の誤りを排除して、キリストのあがないは、最初から選民だけを意図し、あがないの適用も選民のみに確実有効であることを語る文脈で、キリストは選民をすべての敵から守ってあがないを確実有効にしてくださることを表明するのが意図である。キリストの三職、すなわち、預言者職、祭司職、そして、王権が属する王職を表明するのは、第8章第1節である。「神はその永遠のご計画で、ご自身のひとり子主イエスを、・・・預言者、祭司、王に選び、また任ずることをよしとされた・・・」。
第2の個所は、大教理問答45問である。問45 「キリストは、どのようにして、王の職務を果たされるか。」答 キリストは、「・・・彼らのすべての敵を抑制し征服すること・・・」と述べて、コリント一15:25を証拠聖句に挙げて、ここは、キリストの王権を語っている。
第3の個所は、大教理問答52問である。問52 キリストは、その復活において、どのように高くされたか。答 「キリストは、その復活において、次のように高くされた。・・・敵から守り・・・」と述べて、コリント一15:25-27を証拠聖句として挙げて、ここもキリストの王権を語っている。
第4の個所は、大教理85問である。問 死が罪の支払う報酬であるのなら、なぜ義人は、そのすべてがキリストにおいて許されているのに、死から解放されていないのか。答 「義人は、終わりの日に死そのものから解放されるし、・・・」と述べて、コリント一15:26が証拠聖句として挙げられて、キリストが王権を行使して、すべての敵、また、最後の敵として、死を滅ぼすことを語っている。
なお、終末には、キリストは、メシアとしてのみわざを終わるので、人性を脱いで、神性だけに戻ると言う人がいるが、これは、誤りである。ウェストミンスター大教理問答36問の答で、「恵みの契約の唯一の仲保者は、主イエス・キリストである。彼は神の永遠のみ子、み父と同質同等でありながら、時満ちて人となられた。それで、昔も今も引き続き永遠に(for
ever)、二つの完全な異なった性質と、一つの人格をもつ神にして人である」、また、小教理問答21問の答で、「神の選民の唯一のあがない主は、主イエス・キリストです。このかたは、神の永遠の御子でありつつ人となられました。それで、当時も今もいつまでも(for
ever)二つの区別された性質、一つの人格をもつ、神また人であり続けます」と明言されているように、キリストは、永遠に二性一人格である。
以上のように、コリント一15:25-28は、ウェストミンスター信仰基準には、4個所で挙げられているが、終末に、キリストが国を神に渡すことと御子が自ら神に服従することについては、特に、ウェストミンスター信仰基準には何も語っていない。
では、終末に、キリストが国を神に渡すことと御子が自ら神に服従することについて、わたしたち日本キリスト改革派教会の牧師たちは、どのように理解してきたのかと思う。すると、神学校の教科書であったL.ベルコフの「組織神学」(410頁-411頁)による見解で理解してきたと思う。すなわち、ベルコフも、丁寧に読むと慎重に興味深いことをいろいろ述べているが、ベルコフの見解は次のようである。キリストの王権は、教会を支配する恵みの支配(regnum
gratiae)と宇宙(the universe)を支配する力の支配(regnum potentiae)を含む。そして、キリストは、フィリピ2:9-11にもあるように、十字架の死に至るまで父に従順であってので、キリストは、父なる神の右に引き上げられ、あらゆる名にまさる名と王権を与えられ、教会と宇宙を支配し始め、今に至っている。しかし、終末には、コリント一15:24-28に基づき、キリストはすべての敵を征服して、国を神に渡すことにより、キリストの王権の宇宙支配の部分を終るが、教会を支配する王権の部分は、ルカ1:33の「彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない」やペトロ二1:11の「こうして、わたしたちの主、救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります」とあるように、永遠に続くという見解を、ベルコフは述べている。そこで、わたしたちも、そのように理解してきたと思う。
しかし、ベルクーワは、コリント一15:25-28において、パウロは、ベルコフのように、キリストの王権を教会支配と宇宙支配に分けておらず、キリストがすべての敵を滅ぼして勝利し、御国を父に渡し、自らも父に服従したことによって、メシア・キリストの支配と栄光が完成したことによって、神の支配と栄光もすべてのすべてにおいて、明らかになるという意味であって、終末に、キリストの王権が終了したり、消失したり、キリストの人性が最早必要なくなって、人性を脱いで神性だけになって、御子が父に吸収されてひとつになったりを言おうとしているのではないと述べていて、ベルコフの見解より少し先に進んでいると言える。
そこで、わたしたちとしては、コリン一ト15:24-28の解釈については、ベルクーワの見解は、わたしたちが習ったベルコフの見解よりも進んでいるということを知っておけばよいと思う。ベルクーワの見解をいきなり説教したりせず、教師会などで、コリン一ト15:24-28の解釈について、いつか話し合ったら建徳的と思う。